育児において、赤ちゃんの抱っこやおむつ替えなどの動作が手首や腕に大きな負担をかけ、腱鞘炎(特にドケルバン病:親指側の手首の腱鞘炎)を引き起こしやすいのは、主に以下の3つの要因が複合的に関わっているためです。
1. 「テコの原理」による手首への負荷集中
赤ちゃんを抱っこする動作は、手首にとって最も負担のかかる「テコの原理」が働く動きになります。
不安定な重さの支え方
赤ちゃんの体(頭や上半身)の重さを、指先や手首だけで支えようとします。このとき、重さの支点が体から遠い手首や親指の付け根になり、テコの原理で実際の体重よりもはるかに大きな力が腱にかかります。
親指の酷使
赤ちゃんの頭を支えるために、親指を大きく広げて(外転・伸展)、他の指とは違う方向に強く力を入れる姿勢を長時間保ちます。
この親指を広げる、または強く使う動作は、短母指伸筋腱と長母指外転筋腱という2本の腱を酷使し、その周りの腱鞘との摩擦(ドケルバン病の原因)を激しくします。
2. 「繰り返しの動作」と「姿勢の固定」
育児は、腱を休ませる暇がないほどの繰り返し作業です。
頻繁な抱っこ・授乳
赤ちゃんは頻繁に抱っこを求め、授乳(特に哺乳瓶や片手で抱える授乳時)では、特定の姿勢で手首を固定し続ける必要があります。
おむつ替え・着替え
おむつ替えで赤ちゃんの両足を上げたり、着替えで体をひねったりする際も、手首や指に瞬間的に大きな力が加わります。
長時間同じ姿勢
夜中の授乳や寝かしつけの抱っこなど、同じ姿勢を長時間キープすることで、血行不良と筋肉の緊張が起こり、腱や腱鞘の炎症が回復する機会を奪います。
3. 「ホルモンバランスの変化」(特に産後)
産後の女性は、腱鞘炎を発症するリスクがさらに高まります。
エストロゲンの減少
妊娠中から産後にかけて、女性ホルモンの一種であるエストロゲンの分泌量が大きく変化します。エストロゲンには、腱や腱鞘の組織を柔軟に保ち、炎症を抑制する働きがあると考えられています。
産後の急激な減少
出産後にこのエストロゲンが急激に減少することで、腱鞘がむくみやすくなったり、組織が硬くなったりして、腱と腱鞘の間の摩擦が起こりやすい状態になってしまいます。
まとめ
赤ちゃんのお世話は、手首に負担がかかる不自然な姿勢、腱を休ませない繰り返しの作業、そしてホルモンバランスの変化という3つの要因が重なるため、腱鞘炎(特に親指の付け根のドケルバン病)が起こりやすい環境にあると言えます。







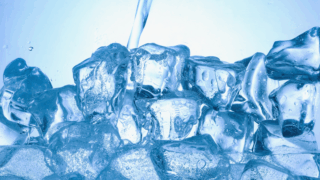





コメント