こんにちは、川路です。
今日は医師との連携を意識していて良かったなと思うような出来事がありました。
骨折が疑われるような場合や、軟部組織だけの影響じゃないんじゃないか?と考えるような場合。半月板などの損傷も考えられるんじゃないか?なんて時もあります。
そういう時は、病院を紹介して検査してもらって、その後に僕が施術計画を立てる事も少なくないんです。
僕が病院連携を行う事で気を付けているのは、「この症状は何かわからないから、とりあえず病院へ」という風に考えてしまう事ですね。
「おそらくこの症状だろう」という答えを自分の中で持ちながら、病院に行ってもらわないと鑑別能力って上がらないと思うんですよ。
逆に、病院との連携を考えずに、自分で治す事にこだわって、いつまでも良くならない施術を続けるのも良くないですよね。あくまで僕ら柔道整復師が資格によってできる施術の境界線は大事にしたいと考えているんです。
「病院は柔道整復師を嫌っている」「紹介しても返してくれない」
こんな事を聞く事もあったので、正直「病院に紹介してもな〜」と思っていた時期もありました。
でも、その時はその時で考えればいいし、まずはやってみようと決めてから、実際にやってみたんですよ。
そしたら、想像していたのと違って、検査の結果を教えてくださる事も多いし、「こうしてください」と指示を貰える事もあります。
医師の診断名と僕が思った状態が違えば勉強になりますし、合っていれば、それは自分へのフィードバックになると思っています。なにより、患者さんが安心して施術を受けてもらえるなと感じています。
僕自身は柔道整復師ですが、鍼灸師を雇っているので、病院連携はした方が良いと思ってやっているんですよね。
そうすると、連携する事や、国家資格者の境界線というのも腑に落ちるようになりました。わからない事も多いですけど、その時その時で勉強して、経験を積みながら頑張ろうと思っています。
さて、来週は鍼灸師の国家試験を受けて学校を卒業する人が見学に来るんです。
柔道整復師と鍼灸師がどうやって連携して施術をしているか、技術面だけじゃない所も伝えられたらなと思っています。
でわでわ。


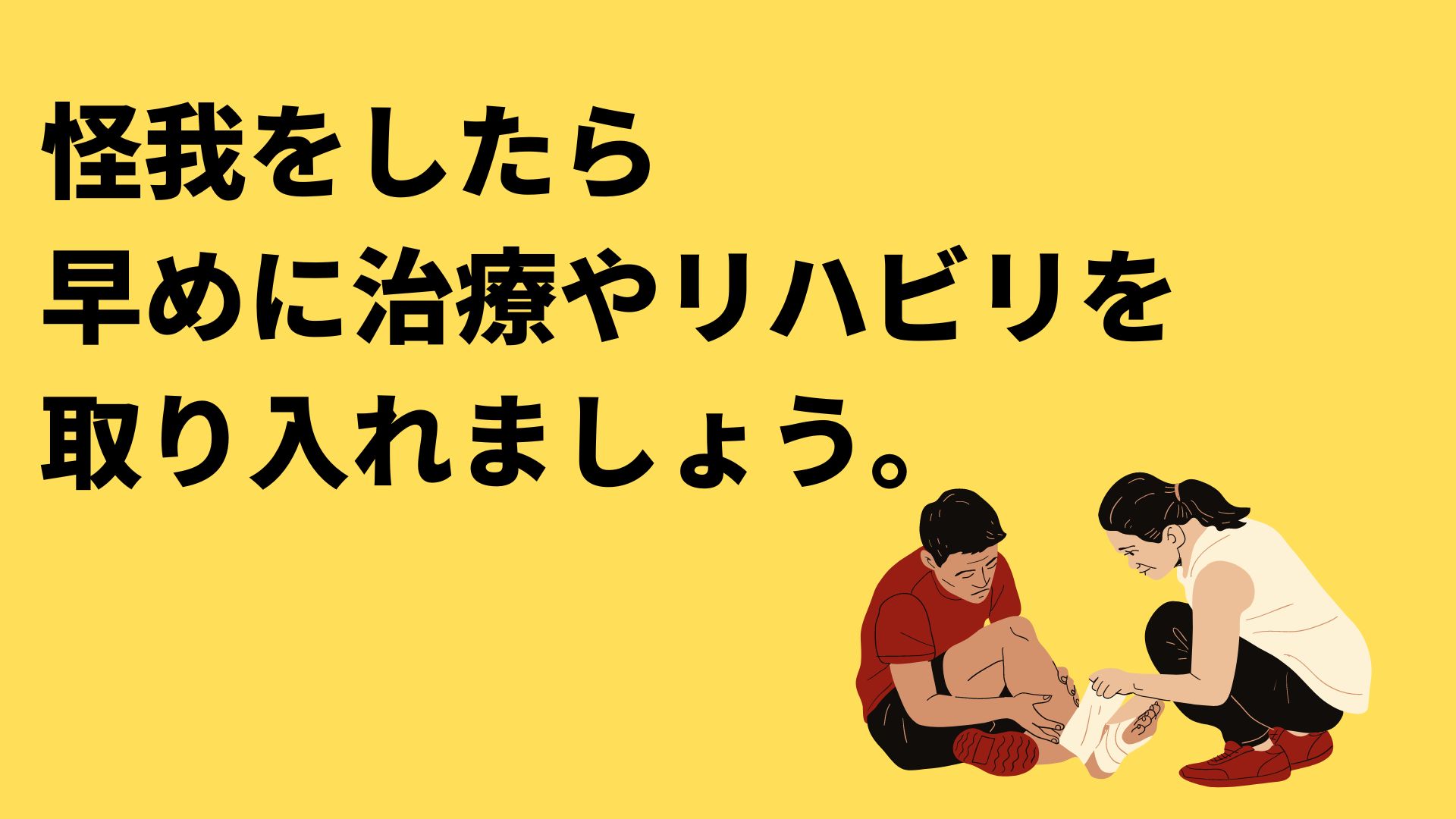
コメント