炎症が起きている部位を冷やすこと(アイシング)が痛みを和らげるのに効果的なのは、主に3つの生理学的な作用があるからです。
1. 血管収縮による「炎症の拡大抑制」
炎症が起きると、体はその部位に血液を集めて治癒を促そうとします(これが赤みや腫れの原因です)。冷やすこと(低温刺激)は、この反応を一時的に抑制します。
血管の収縮
冷却により、患部とその周辺の血管が収縮します。
血流の減少
収縮によって血流が減少するため、炎症によって過剰に集まっていた血液や炎症物質の供給が抑えられます。
腫れ・むくみの軽減
これにより、炎症による**腫れやむくみ(浮腫)**の拡大が抑えられ、腱鞘内の圧力上昇が緩和されることで、痛みが軽減されます。
2. 知覚神経の麻痺による「痛覚の鈍化」
冷たさは、痛みを伝える神経の働きを一時的に鈍らせる作用があります。
神経伝導速度の低下
冷やすことで、痛みを脳に伝える知覚神経の活動(伝導速度)が遅くなります。
痛覚閾値の上昇
いわば、痛みを感じるセンサーの感度が一時的に鈍くなるため、痛みそのものを感じにくくなります(麻酔効果に近い作用)。
3. 細胞の代謝活動の低下
炎症とは、組織が損傷し、それを修復しようとする一連の反応です。
代謝活動の抑制
冷却は、炎症部位の細胞の代謝活動を低下させます。
二次的な組織損傷の軽減
これにより、炎症反応に伴って周囲の正常な組織までが損傷を受けるのを抑制する効果(二次的な低酸素損傷の抑制)が期待でき、炎症の進行を穏やかにします。
まとめ
腱鞘炎で炎症が起きている(急性期で腫れや熱を持っている)場合、冷やすことは「炎症の拡大を抑え、腫れを軽減する」と同時に「痛みの感覚を一時的に鈍らせる」という両面から、つらい症状を和らげるのに有効なのです。
ただし、冷やしすぎは凍傷の原因になるため、アイスパックなどをタオルで包み、1回あたり15~20分程度を目安に行いましょう。
また、慢性期(熱や腫れがない場合)の血行不良による痛みには、逆に温める方が効果的な場合もあります。







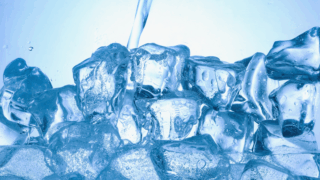





コメント